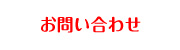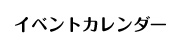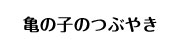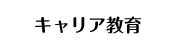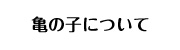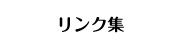春の海ひねもすのたりのたりかな。菜の花や月は東に日は西に 与謝蕪村
2025/03/11
この俳句は、江戸時代の春の海を詠んだものですね。菜の花やも春の長閑な時を詠っていますね。どうも、蕪村は、松尾芭蕉に憧れて、旅をして、詠っています。蕪村は、1716年に誕生していますし、松尾芭蕉は、1694年11月に亡くなっていますので、憧れる存在とは、いいものですね。だいたい、日本人って、私が歴史好きだから、よりそう思うのかも知れませんね。そして、この江戸時代の春の海も、菜の花も、今から319年前の海も、今の海も、地続きで、令和の今でも、この春の海ひねもすのたりのたりかなも、菜の花や月は東に日は西にも、令和の私たちが、詠んでも、その情感は、同じだなぁと、とても嬉しく感じたところです。特に日本人は、月を観たり、夕陽を見たりして、感性を磨きます。それも、日本海に沈む夕日が、水平線に沈む瞬間も見ることが出来ます。それを、あの沈む瞬間を、「ジュっ」と、表現した人がいたのです。なるほどなぁと、だから、日本人は、自然界溢れるところに生活していますので、より、感性が磨かれるのでしょうね。そういえば、今、日本は一極集中となり、東京はビルディングが連なり、自然界とは程遠い感じがします。そういえば、高村光太郎の奥さんの智恵子がいたのですが、その「智恵子抄」の詩があるのですが、「智恵子は東京には空が無いといふ、ほんとの空がみたいといふ、、、、、、、智恵子は遠くを見ながら言ふ。安達太良山の山の上に 毎日出ている青い空が 智恵子のほんとの空だといふ。あどけない空の話である。昭和16年に出版した。
だから、都会には自然は、無い。だから、人間の感性を磨くことはとても難しいと思う。とてもじぁないが、
春の海ひねもすのたりのたりかな。菜の花や月は東に日は西に。など詠めるはずがない。都会の雑踏の中では、感性を磨くことは、とても難しいと言える。そのことに、日本人は早く気づく時ですよ。と、忠告したいですね。