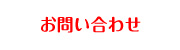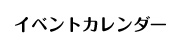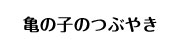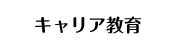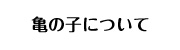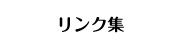大人の教養・読んだことある❔ 古事記と日本書紀❔
2025/03/04
古事記と日本書紀は、日本神話や古代史を記した現存最古の歴史書です・。まとめて「記紀」と呼ばれています。
実は、誰もが知っていますが、実際に読んだことがある人は少ないかもしれない。と言うのも、大東亜戦争中までは、軍国主義教育の支柱として学校では教えられてきましたので、戦後はGHQにより、全く教えられなくなりました。しかし、戦後80年経過してきた我が国日本が、政治家も官僚も、我が国の「国益」が何であるのか、すっぽり抜け落ちている居るのです。じつは、このことは、宮家邦彦氏の言葉を借りれば、ポピュリズム化した日本人が出て来た。(政治改革を目指す勢力が既成の権力構造やエリート層を批判し人民に訴えてその主張を目指す運動です。)小泉首相の時です。竹中平蔵氏もポピュリズムですし、唯物論者です。だから、今日本中は、その「つけ」があっちこっちで、発生しています。デジタル社会だから、「キャシュレス」で決済だ。と、すると、お地蔵さんめぐりをして、お賽銭を供える。すると、「日本の1円も廃止すればいい。」とか、「キャシュレス社会にすればいい」とか、好きなことをめいめい勝手に発言だ。すると、宮家邦彦氏は、「1円に笑うものは1円に泣く」と。すると、日本人は「やっぱり、お賽銭文化だよね。」と、やれやれです。
先ず、「古事記」が先に書かれている。飛鳥時代に天武天皇が、暗記が得意な28歳の側近・稗田阿礼(ひえだのあれ)に命じて、天皇家の歴史である「帝紀(ていき)」と、豪族の神話や伝承である「旧辞」を覚えさせたといいます。そして、稗田阿礼がそらんじる内容を太安万侶(おおのやすまろ)が文字に書き起こし、奈良時代の和銅5年(712年)に完成したと伝わります。当時、日本語には話し言葉しかなく、固有の文字がありませんでした。仮名文字が生まれる前の時代だったのです。そこで太安万侶は、稗田阿礼がそらんじる日本のことばの意味を漢文(古代中国の文字)に置き換えたり、あるいは言葉の意味を漢文で表したりと、苦心して文章化していったそうです。内容は神代(かみよ)~神様が始めた時代から推古天皇の治世までで、人物を軸に話が進み、上巻・下巻・中巻・下巻から成ります。
どうも、古事記の方は、日本人向けに書いてあります。出雲王朝~国譲り神話が記載してあり~天孫降臨し、力比べし、諏訪の国に。諏訪大社、狩りを許す。鹿の国(祭事)~出雲大社(現存の大社)国譲りが成立する。~神武東征~ヤマト朝廷(奈良の橿原神宮にて、神武天皇)~用明天皇~厩戸豊徳耳命(聖徳太子)~崇神天皇~推古天皇までが書いてある。
そして、「日本書紀」は、同じく天武天皇のもとで、国の歴史書の編纂が命じられ、天武天皇の皇子・舎人(となり)親王をはじめ多くの人々が携わって、40年ほどの歳月をかけて養老4年(720年)に完成されたと伝わっています。なので、「日本書紀」の方は、対外向けに作成されたと言える。国家の史料としての要素がある。
だから、私たちが知っている因幡の白兎も、スサノオやヤマトタケルなどの性格が大きく異なったりしている。
「古事記」には、そこいら辺りが詳しく書いてある。
いやはやですね。我が国、日本はやっぱりすごい国でしたよ。
あぁ。浦島太郎物語り、竹取物語、桃太郎も、日本の昔話は、いやはや、面白いです。