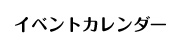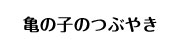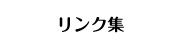お早うございます。の続きです。
2017/02/14
その13才の少年は、両親から虐待をされ、食べるものも他の兄弟姉妹とは、明らかに差別されていた。つまみ食いなどすれば、折檻され、縛られては、鞭や竹の棒で叩かれていた。学校へ行っても、臭い臭いと言われ、友達にものけ者にされていた。唯一の友達は、子犬の「しろ」だけであった。そこで、居たたまれなくなり、家出をすることになり、足尾銅山の洞窟に住むことになった。子犬の「しろ」は、置いていくつもりだったが、子犬の「しろ」が後から追ってきて、一緒に洞窟で住むことになった。昭和34年頃の日本は、まだまだ、戦後の貧しい農村で、電気製品も、水道も、テレビもガス整備も、未開発の時代であった。勿論、車なども普及もなく、とても、のどかで、のんびりしていたような気がする。今思えば、案外、いい時代だったような気がする。そんな時代だったのに、こんな少年が居たのだ。そして、この少年は、実に逞しく生きることに、真っ直ぐ向き合っていた。山の中の木の実やキノコを食べ、兎や、へびを捕まえて、食べ、イノシシを落とし穴に誘い込み、生け捕りし、生きることに必死であった。少年は、子犬の「しろ」に、助けられ、生きていく相棒として深い愛情を重ねていた。しかし、子犬の「しろ」は、亡くなってしまった。少年は別れ難かったが、洞窟を去ることになった。ここで、少年の転機が到来し、洞窟から抜け出した時に、老夫婦に出会い、その老夫婦の子どもになって暮らして欲しいと、所望された。ここで、美味しいご飯に出会い、お風呂に入り、お布団で寝ることができた。でも、これで本当にいいのか、決められない少年が居た。それは子供のころに虐待され、叱られてばかり育った少年にとって、人を信じることは無理なことだった。洞窟で生きていた時は、人の想いなど考える必要はなかった。自分がどうしていいか分からなかったのだろう。思春期特有な時期だったことだろう。その少年は、その老夫婦と別れることになった。
服や靴やカバンを揃えてもらった。財布にお金も入れてもらった。 そんな少年は、また山に入り、洞窟で住むことになった。 ある時、村の広場で、物売りをしている人を見つけた。よ~く見ると、野山の山菜を一盛り、300円で売っているのを見つけた。これなら、山菜がどこにあるのか知っているので、その広場で、売ることになった。そこへ、蘭のバイヤーがやって来て、珍しい蘭を知らないかと問われ、知っているので、沢山の珍しい蘭を売ることになった。その時に、お金の価値が分からず、そのバイヤーさんに教えてもらっていた。カレーライスなども値段が分からず、支払いしても、お釣りが分からず、お金の計算も出来なかった。結局、そのバイヤーさんにも、安い価格で売っていたことになり、騙されていたことに気づいた。 ここで、益々、人間不信に陥ってしまった。もう、生きていてもつまらないと、思い、静岡県の富士山の麓の青木ヶ原樹海で死のうと思い、トラックに載せてもらい。到着し、その樹海に入っていく、何日も歩き、白骨化したものを見たり、首をつっている遺体を見たりしているうちに、死ぬのが嫌になり、トラックを見つけて、川の方へ行くことになった。
実は、前半がここで終わってしまった。
終わっても、中々、心が落ち着かず、調べてみました。その洞窟おじさんの現況が載っていました。
その加村一馬さんは、今現在、群馬県の社会福祉法人「三和会」の障がい者支援施設で、住み込みで働いておられるとのことでした。そこで、子どもさん達に、子どものころ虐待があって、人間不信になったけど、人間は、必ずややり直せると、お話をされているとのことです。
私は、やっぱり人間は凄いなぁ!と、感動しました。