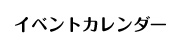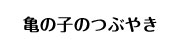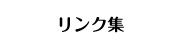青天の青空です。気持のいい朝です。
2022/05/24
柿本人麻呂の歌に、三瓶山の浮き布の池で詠んだ歌がある。
『君がため 浮沼の池の 菱摘むと わが染めし袖 濡れにけるかも 』
飛鳥の時代のことですね。柿本人麻呂は、大宝元年(701)以後のことである。石見の国司に任じられた。国司といっても「守(かみ)」ではなく下位の国司だったと言われる。持統天皇・文武天皇に仕え、数多くの優れた歌を残した宮廷歌人として、華々しい軌跡を描いた人麻呂は、一転して、鄙ひなの石見に下向しなければならなかった。人麻呂は幾人かの妻を持っていたがとりわけ軽かるの里に住む女を深く愛していた。その女が死んだときに人麻呂は悲しみ悲嘆の消えぬ間に石見に下る命令が追い打ちをかけた。すでに、五十路いそじの坂を越えていた頃のことである。その人麻呂は、下向した石見の国に入った時に、目の覚めるような石見の碧い海を見た時、思わず息をのんで立ちつくした。大和では決して見ることのない、鮮烈な海が広がっていたのである。断崖の海辺をいくつか越えると、やがて単調で荒涼とした都野津つのづの海岸へ着いた。人麻呂は限りなく広がっているこの単調な海辺が奇妙に印象深かった。それは、傷ついた魂をいやす不思議な海だった。着任してどれほどの時が経ったろうか。人麻呂は土地の長者の家で美しい娘、依羅娘子(よさみのおとめ)に出会った。まだ、17.8だろうか。いかにも清楚で従順な乙女だった。すでに、老境にあった人麻呂は、情熱の残り火のありったけをかき集めて、彼女との愛に燃えた。決して辺土のかりそめの遊びではなかった。人麻呂の柔和なまなざし、しっかりと包みこむおおらかな情愛に、依羅娘子は身も心も投げ出し、ひたむきに人麻呂を求めていった。人麻呂は、虚栄に満ちた都の女とは全く違った彼女に、清冽(せいれつ)な魂を感じたのだろう。彼女のみずみずしい肌に触れるたびに、ともすれば荒ぶる人麻呂の心は和められ、この異郷の地で知り合った若い妻に、若者のような生命の息吹きと、新鮮な感動、さらに詩歌への新たなる意欲をかき立てられたのであろう。もはや片時も、依羅娘子のもとを離れたくないほど、人麻呂の愛は深まっていた。だが、こうした逢う瀬もそう長くは続かなかった。
三瓶山は、人麻呂さんと、依羅娘子とのデートスポットでした。
令和に蘇る。石見の宝、柿本人麻呂さんです。凄い歴史ある石見路ですね。